ずっと記事にしようかどうか迷っていたのですが、いろいろと質問でも受けたり、聞かれることが多くなってきたので、今回は思い切ってこの話をしようと思います。
みなさん多かれ少なかれ、「アート」と「アートじゃないもの」を区別している場面があると思います。やっぱり美術館にあるものはアートな気がするし、例えば似顔絵とかはアートじゃない気がする。不可解な作品はすごいアートっぽいし、なんかわかりやすい動物の絵はアートじゃない気もする。そんな曖昧な”境界線”は、みなさんなんとなくイメージができるはずです。
ということは、やはり皆さんは「アートとそうじゃないもの」の違いはどこかにある、ということは共通して納得できる部分なのかなと思います。なんでこの定義づけが必要かと言うと、3歳児の絵を例に出して、「子供はみんなアーティストだ」というようなフレーズがあったりするので、ここでは何でもかんでも感情的な部分でそういう話をするのではなく、理論的に理解をして、最終的に美術的価値とはなんだろうかと言う部分に着地したいので、少し回りくどく話を進めますね。
本当はこのままあいちトリエンナーレの問題となった作品たちは、「果たしてアートだったのか」と言う部分にも行こうと思ったのですが、長くなれば別に分けようと思います。
追記(2022/05/18)
歴史的な根拠に基づいた、もうちょっとガッチリしたカテゴライズの話はこちら↓
【保存版】「art」と「芸術」と「アート」と「美術」の違いとその定義
もうちょっと整理した話はこっち↓
【保存版】アートとそうじゃないものの本質の話
まずはじめに いろいろとまとめておきたいこと。
最初に言っておきたいことは、ここで私は別に「これがアートだ!」と言う主観的な部分を、皆さんに押し付けようとする気は一切ありません。私は自分でもアートをまだ全然理解できていないと思っていますし、それを勉強するためにドイツの大学に行って、そしてまだ研究をするためにオランダに来ています。ですのでまだまだその途中で、その答えを探すために制作を続けているということだけご理解いただければと思います。
今回の話は、上で話した個人個人の“境界線”の引き方をもう少しはっきり理解するための漠然とした前提の部分だと思ってください。
一応話を進める際に、この話の中では「美術=art / アート」、そして「芸術=クリエイティブなものすべて」として定義しておきます。これはただ今回のみの利便上のもので、言葉の定義の話は今回視野にいれていませんので、他意はないと思ってください。ただ理解しやすくなるかなと思っただけです。ここではこの5つのワードを統一せずに話が進むと思いますが、私の文章力と雰囲気の問題ですので、混乱しないようにお願いします。
区別をする境界線の話をしたいだけですので、美術と芸術どちらが優れているかの話はしていません。別物です。野球とサッカーです。
…….
2020年8月 追記
いろいろ考えていると、私が意図している、ここで使っている「アート」は、「現代アート」として置き換えて読んで頂いた方がわかりやすいと思います。
……..
日本中でよく聞く アートという便利な言葉
日本だけってことはもちろんないのですが、日本では特に、「アート/アーティスト」という言葉は多様性を含みすぎています。○○アートとか、アーティスティックとか、ミュージシャンのこともアーティストだし、デザインもなんでもアートになってしまう世の中。別に言葉なのでそれはどうでもいいと言われればそうなのですが、ごちゃ混ぜにしてしまうことで何が起こるかというと、思考の停止が発生するんです。芸術とは得てして、大抵のものは審査され評価され、講評されるものだったりします。つまり、芸術としての価値やレベルを様々な角度から見られ、評価をします。ですが芸術全てをアートにしてしまうと、「これはアートなのか、このアートはアートしての価値がどれくらいあるものなのか」という評価を下す際の思考ができなくなってしまいます。 これは例えば、野球とサッカーを球技だからって同時に論議にかけているような状態です。まさに今日本はそんな状態です。そんなレベルです。ボールの大きさもルールも全部違うのに、そんな細かいことは見ない、考えないで、球技だから同じだっていう感覚でその両方を見て楽しんでいます。時にはこれは野球じゃない!と言い出したりして炎上したりします(あいちトリエンナーレ的な)でも、言ってる人たちが、野球が何かサッカーが何かをあんまり考えたことない人ばかりです。もっともっと目を凝らして、思考を巡らせれば、いろんなことが見えて来て、その二つは別のものなんだと理解することができ、そしてそれにまつわる知識を手に入れることで、ちゃんと評価ができるようになります。
美術的価値とは何なのか ということをまず理解する
このブログではよく出て来ますが、アートは学問です。世界中で研究され、美術の大学があって、一般大学でも美術を歴史的観点から分析する美術史という学問分野が確立されています。他の芸術がいかに素晴らしいものだとしても、この美術的な学問的な価値を保有していない作品は、美術作品(=アート)とは呼ぶべきではないと思います。ここが前提。
「では美術的価値とは何なのか?」ということになりますね。 美術とは多くの場合、アンチテーゼだったりします。つまり過去の作品の影響を受けて成り立っているということです。ですので一番わかりやすい美術的価値に直結する考え方は、「(美術)史学的価値」を保有しているかどうかという考え方がひとつあります。少し例をあげてみましょう。

Des glaneuses (1857)
Jean-François Millet(1814-1875)
これは皆さんも知っているミレーの『落穂拾い』です。これを美術史学的に見ていくとこういったことになります。
19世紀は写実派(レアリズム)の時代でした。その中の一つとしてバルビゾン派があります。それまでの風景絵画は、キリスト教会が中心だった際は、宗教絵画。貴族が力をつけたら貴族絵画という背景に使われていました。またロマン派では、戦争を舞台にした人々の感情だったり、大自然との対比だったりと、非日常の世界と感情に目を向けたものでした。そう言ったこれまでの題材ではなく、「もっと身近な自然を描こう」と言った時代です。(アンチテーゼの部分ですね)
特にミレーたちバルビゾン派と呼ばれる人々は、バルビゾンという村に身を置いて、その地域の貧しい農民たちや、森の風景に目を向けました。技術的なことをさらに付け加えると、これまで油絵の具は、顔料を砕いて油で溶いて…という大掛かりな作業が必要で、外でスケッチをして、アトリエで本制作することが当たり前でしたが、1841年頃にチューブ絵の具が発明されたことによって、画家たちが外でイーゼルを立てて、そのまま油絵を描けるようになったことも忘れてはいけません。この作品は3人の貧しい農民女性を描いていますが、やわらかい背景の描き込みや、平行線で描かれた構図によって、三人がふわっと浮き出るような、絵画としての技術の高さも見て取れます。内容としては、聖書の内容も含まれているとされています。この女性たちは忙しく農作業をしているわけではなく、農民よりもさらに貧しい人々で、刈り入れが終わって残った落穂を拾わせてもらっている女性たちです。つまり、貴族たちから見たら農民は貧しい人々でしょうが、この女性たちはさらに貧しい女性たちでした。
このバルビゾン派は、”写実的に絵を描く”という技法的な部分だけではなく、貴族たちは知る由もない世界でこんなにもたくさんいる農民 たちの現実という”意味の写実性”を捉えたということです。もちろんこの作品は後に、パリの王立絵画彫刻アカデミーが開くサロン・ド・パリに出展しますが、貧しい人々描く絵画を受け入れられず大批判を受けます。
長くなってしまいましたが、私が暗記しているこの絵画の背景とその内容です。(間違いがないように書籍をできるだけ確認しながら書きました。上の部分に間違いがあれば教えてください。)
話を戻しながら例に沿って進めていきます。この有名な絵画の、どこに史学的価値があるかを確認していきましょう。特にアンチテーゼの部分が重要ですね。風景というものはそれまでは、あまり主題となることはその時代まではありませんでした。例えばルネサンスなどの宗教絵画では、神がどこにいるのかを示すためだったりするもので、背景には背景として、風景に意味がありました。ですがバルビゾン派ではミレーやコローの作品など、風景を風景として捉えた初めての作品でした。
さらに上でも書きましたが、技法的に写実的に描くという部分よりも、誇張表現が多く含まれていたファンタジーに近いような貴族絵画や、非日常の一瞬や感情を取り込んだロマン派絵画ではなく、一般農民のありのままの世界を描いたという”意味の写実性”を捉えたことがなによりも新しいことでした。
写実主義とはもちろん写実的に対象を描くということも含まれていますが、それは新古典主義の方に見られたことです。それよりも、中身の意味としての写実性に注目をしました。今まで避けていた部分の描写などが特にそうですね。(貴族に対しての農民や、クールベのL’origine du monde (世界の起源)という作品では、女性の股間部分を切り取った絵画でした。)
つまりこのことを通して何が見えてくるかというと、史学的なアンチテーゼを行うということは、過去のもの(それ以前のもの)を知り、それを受け取ったのちに、いかにして新しいものを作るかという部分が評価される一つのファクターだということです。ですのでこのブログでも多く言っている、「(過去の自分を含めて)日本人作家は美術史を勉強しなさすぎる」ということを一つ問題としたいなと思います。
“美術的価値”の大きな部分のひとつ、”史学的価値”とは
「過去を知ること」を通して、その作品の内容が歴史的な「新しい意味」を保有しているかどうか。
この部分が非常に大切なことです。もちろん技法が新しいことも重要になり得ますが、
技法だけ新しいことを求めても、それは美術的価値が高いとは必ずしも言えません。なぜならそれは工芸の部分でも同じことを当てはめることができるからです。それは技術革新とも言えます。スキルの差とも言えます。そう言った作品の外見の部分ではなく、美術史という長い線上で、作品の中身の部分が新しいかどうかが重要になります。
これはもちろん作る側も必要な見解ですが、作品を見る側の一般の人々や、審査や評価をする人々にも求められる前提部分です。
見る側の人々も、美術作品を解釈する上で、感性だけではなく、知識を身につけることが必要だということです。
そしてこの美術的価値があるかないかで、アートかどうかを判断することも可能かなと思います。クリエイティブで素晴らしい作品だとしても、それはアートじゃないという作品も非常に多いのです。
案の定、
長くなったので分けたいと思います。
part 2はこちら (投稿次第リンクになります)
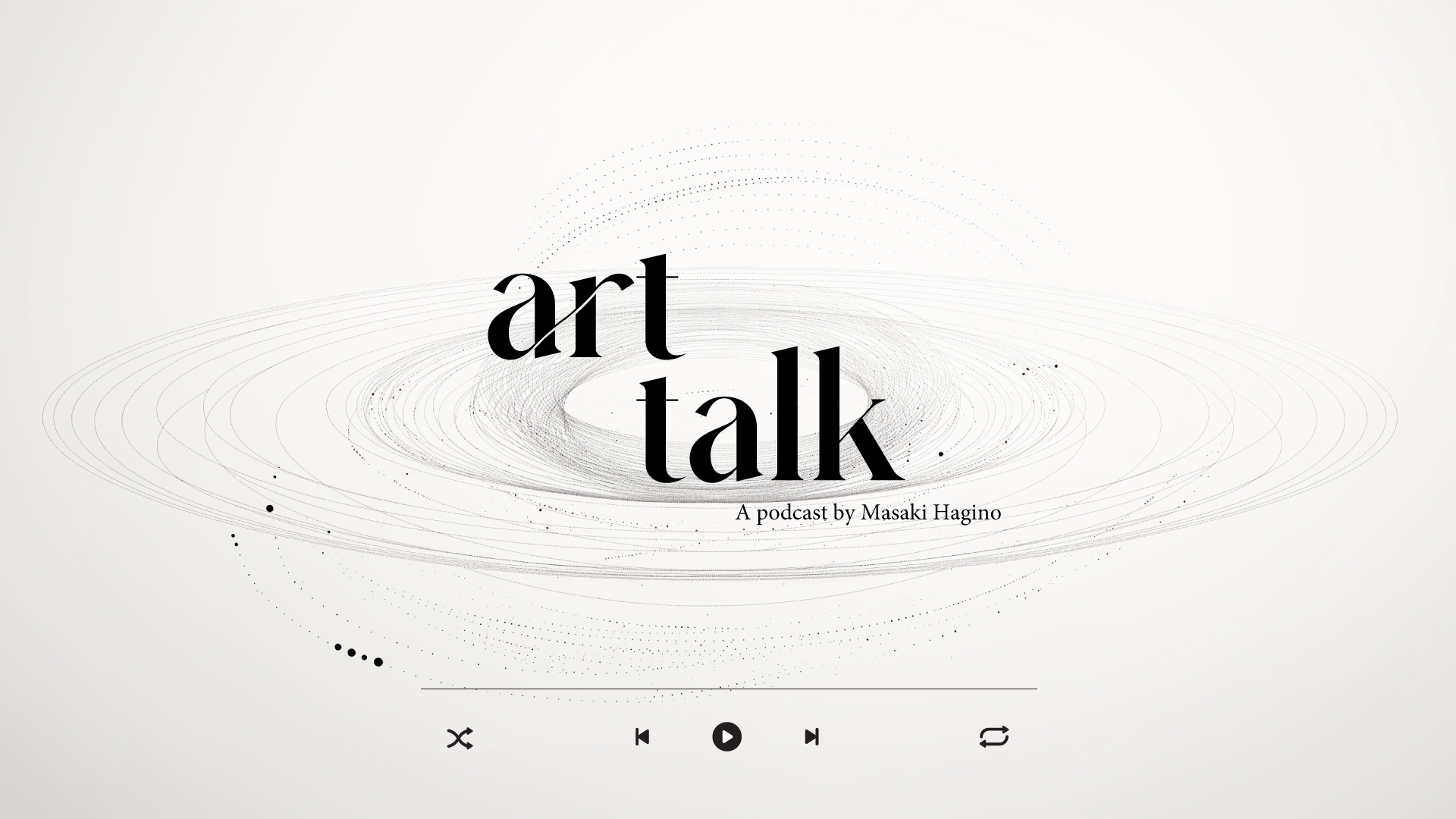



コメント
[…] 前回part1の記事では美術的価値を持たないものは、美術/アートとは呼ばずに、芸術として扱うべきだという話をしました。 言葉の前提などはpart1の方でまとめていますので、そちらを先 […]
[…] この記事、申し訳ないので ミレーの『落穂拾い』については、別記事(何がアートで、何がそうじゃないかの話 part 1)ですでに一度解説をしていたので、抜粋して以下に。少し絵の解説 […]
[…] ート」として扱っているので、ごちゃごちゃになっているパターンです。そして多分日本作家の多く、8割以上は②に該当すると思います。(何がアートで何がそうじゃないかの話参照) […]
[…] れはきっと絵画だけではなく、他の媒体にも当てはまるだろうなと思います。何がアートで何がそうではないかということに繋がりますが、何を求めて制作をしているのか、作品を通した […]
[…] たから」そして、「一番最初に、あの作品を発表できたから」です。ここら辺は何がアートで何がそうじゃないかの話あたりでも話しているので、気になる方は別記事で。現代美術は研 […]
[…] ・アーティストとして美術を研究するって一体どういうこと? ・何がアートで、何がそうじゃないかの話 part 1 ・何がアートで、何がそうじゃないかの話 part 2 […]